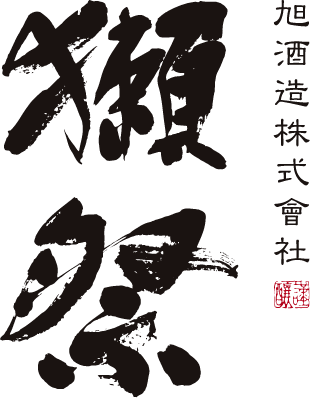酒蔵の増築に着手しました。奥側にあった倉庫を壊して酒蔵を増築します。工事は一期と二期に分かれていて総工期は三年を越す予定ですが、全て完成すれば、従来の木造部分(築230年!!)と合わせて3千平方メートル弱の一部4階建ての醸造庫が完成します。
お陰さまで、皆様に可愛がっていただき、各地の酒販店さんや卸さんから入るありがたい新規取引の申し込みも泣く泣くお断りしているにもかかわらず、売り上げの伸びが製造能力の限界を超しそうです。やはり能力を超えるような無理を続けますと品質が落ちます。だからといって「過度に品薄感を煽ることはしない・酒のまぼろし化を販売促進のための戦術としない」と言い続けて来た私としてはこのままで良いとは言えません。それで、増築を決意した次第です。
小さな酒蔵には不似合いな大きな醸造蔵で、「なんだ・・・旭酒造もついに、大量生産・大量販売の魔力に勝てなかったんだなぁ・・・」と言われそうなんですが、この大きな酒蔵の建物には理由があります。まず、旭酒造は純米吟醸しか造りませんから、一タンクごとの仕込み規模が小さいんです。仕込みの白米規模にして750kg~1500kg用の小さな仕込みタンクを数多く並べる計画です。スペース効率や人件費効率の良い大型タンクを導入しません。
理論的に言えば大きな仕込でも吟醸仕込は可能のはずですが、実際はうまく行きません。少なくとも、弊社の技術水準で吟醸の大型仕込は出来ません。と、いうことで、結果として製造能力に比べて大きな蔵にならざるを得ませんでした。
また、山村の悲しさで土地がありません(注)。上に伸ばすしか余地がありません。平屋でゆったりした建物のほうが酒蔵としてはふさわしいし、スペース効率も優れています。(つまり、エレベーターや階段スペースが要りませんから)しかし一部四階の三階建てとせざるをえませんでした。なんせ、通常は酒蔵の敷地内に建てる精米工場でさえ土地が無いものだから6km以上離れた地元周東町の中心部に土地を求めて建てたぐらいです。(尤もここは敷地だけで3千平方メートル以上もあるものですから、町の人からは「ついにここに酒蔵を建てて山奥から町中に移転して出てくるのか」とずいぶん誤解されました)
とにかく建築は走り始めました。そのうえ、今期、間に合わなくて40俵張りの精米機を一台増設しました。うーん、総額ではいったいいくら掛かるか気の小さい私には計算したくないような金額が見積書の上には並んでいます。当分、社長車は中古車と縁が切れそうもありません。新車は遠い。ま、一生無理だな。でも、いいか。
酒蔵が趣味なんだから。
(注)実は過疎に泣く山村というのは不在地主がけっこう居て、彼らからしてみれば土地としての資産価値がないと思われてるものですから、宅地などもわざわざ植林して山林にされてしまったりして、ますます土地不足になり、その結果さらに過疎が進むという悪循環があります。
過疎対策は補助金より、土地の流動性を高める法整備を進めるほうが過疎対策になるように思いますねぇ。