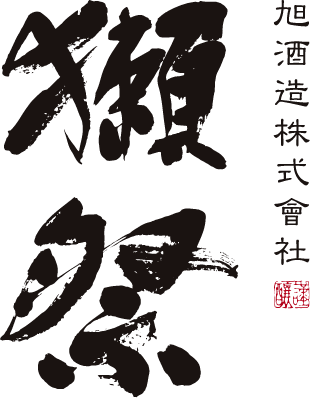先日、NHKのクローズアップ現代を見ていると、国産初のジェット旅客機の第一陣の納入先が決まったとの話を流していました。つい、数年前まで日本のこの分野への参入はおそらく不可能と言われていたのに素晴しい事と思います。
あまり詳しくはないんですが、なぜ不可能と言われていたかと言いますと、アメリカに受け入れてもらえないだろうと政府と業界の腰が引けていたのが原因と噂されていました。
「ゼロ戦」や「隼」の例を引くまでもなく日本の航空機製造の技術水準は非常に優れたものだったと思います。つまり、アメリカにとっては日本がもし本気で参入してきたら自国の航空機産業にとって強力なライバルが生まれるわけですから徹底的に邪魔をするだろうと踏んでいたんですね。(ここまでは噂です)
そんなこともあって、(ここからは事実です) 日本の航空機産業は優秀な遺伝子を持っているにも関わらず、アメリカのボーイングなどの下請けに甘んじていました。
ところが近年、アメリカの航空機産業は工賃の安い中国などに下請けをシフトし始めたそうです。こと、ここにいたって、生き残りのために自社での開発を決断したということのようです。
やっぱり危機って効くんですね。日本のバブル崩壊でアメリカで日本企業の駐在員や日本人社会のみを相手にしてきた老舗の和食店がつぶれ、勤め先を失った板前さんが自分たちで開いた新しい店が現地富裕層のマーケットを開拓して今のアメリカの和食ブームを造ったという話もありますし。
そんな話を聞くと、わが業界のことを思いだします。最盛期950万石売れていた日本酒が350万石をきろうかという体たらくです。まさに、日本のマーケットからNOを突きつけられているといっても過言じゃありません。
だけど、このピンチこそ大きなチャンスと思います。日本酒は変わらなければいけない。中身も変わらなければいけませんし、マーケットも海外も視野に入れた再構築がいると思います。
日本酒は日本の民族の酒で、日本の均質な平等社会から生み出されたものであるが故の強みと弱みをもっていると思います。強みは世界の醸造酒の中でも群を抜いて洗練された品質です。日本の均質な平等社会は労働者なのに自ら責任を持ち工夫する杜氏という職能を生み出しました。この杜氏の存在が日本酒の洗練された品質を造り出した大きな要素です。
弱みは日本の社会と文化から生み出されたものであるがゆえの逆風と限界です。たとえば今でも皇室主催の公式晩餐会の使用酒はワインです。高級料亭なんかもワインの品揃えには自信があるが日本酒は出入りの酒屋の言うとおりみたいなところが多い。うちの常務の話によりますとニューヨークで日本酒の魅力に目覚めたアメリカ人が日本酒を飲みに日本に行くと「日本人は日本酒は美味しくないと言ってる」と言い出す人が2~3割いるそうです。
限界は欧米の階層社会から生み出されたワインと比べるとよく分かりますが、価格に広がりがないこと。よく、「日本酒はだめだなぁ。ワインのロマネコンティのように数十万円のものがない。せいぜい一万円じゃないか」と、言われて、「単純に液体の美味しさで勝負するなら、本当に数十万円のワインと一万円の日本酒に価格ほどの差がありますか? そんなに負けてますか?」と聞き返していました。
液体の優劣にこれだけの差はつかないでしょうから、結局、ワインは欧米の階層社会の文化が生み出したものだし、日本酒は日本の文化が生み出したものです。ここにこの差が生まれると言えます。
実は今、このピンチの中にこそ弱みを強みに転換できる大きなチャンスがあると感じています。国内で逆風が吹くとすれば海外に販路を拡大すればいいでしょうし、そのマーケットで競争に晒されるということは業界の体質強化につながると思います。何よりこの変化は結果として日本国内のお客様にプラスとなって帰ってくると思います。それと、国産ジェット旅客機万歳!!!