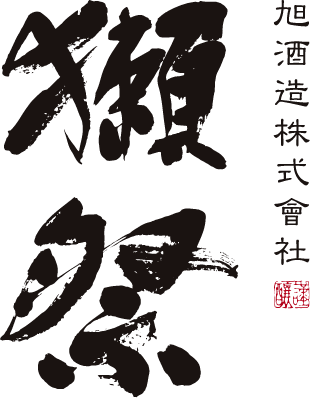刺激的な題名ですが、一昨年から取り掛かっています酒蔵の増改築工事の二期工事が始まり現在の仕込み蔵を取り壊し始めました。この建物は昭和50年に前社長の父の手で建てられた鉄筋コンクリート製の一部二階の平屋建ての酒蔵ですが、手狭になったもので延べ床面積800坪弱の三階建てに建て替えを決意したものです。
職人さんたちが取り付いてまず電気関係から外し始めましたが、その作業を見ていると感慨深いものがあります。
昭和50年というと史上最高に日本酒が売れた年で、現在300万石台に落ちている日本酒の売り上げが950万石を記録し1000万石も夢ではないといわれていた年です。当然、父の立てた酒蔵も当時の「行け、行け、どんどん」気分を濃厚に持つ普通酒専用の大型仕込方式の酒蔵でした。
しかし、私が父の死去とともに酒蔵を継いだ昭和59年にはすでに全国で日本酒は退潮期に入っておりました。その上、旭酒造は近隣の酒蔵との販売競争に一人負けの状態で昭和50年の売り上げに対して6割減。前年比では85%という最悪の状態でした。
当然、決算も最悪で毎日の資金繰りに終われる毎日。そのまだ新しさの残る仕込み蔵と実質債務超過の決算書を眺めながら、「何でこんな馬鹿な建物を建てたんだろう。この金があったらなあ」と父のことを恨んだことを思い出します。
しかし、いくら亡き人を恨んでいても解決しません。とにかく廃業した酒蔵から小仕込に使える小型タンクを安く譲ってもらい、トラックを自分で運転して積んで帰りそれまでの大型タンクと入れ替えたり、タンクの周囲にエプロンのようなものを作って氷を周囲に詰めて冷やせるようにしたり、もちろんそれだけでなく氷蓄熱槽のような当時の旭酒造にとっての年間の設備投資能力を一つで超えてしまうような身の丈に余る過大な設備投資もしながら、さまざまな改造を加えました。
実際に金繰りに苦しんだのもこの頃です。毎月の月末は綱渡り状態。にもかかわらず、設備投資資金や人件費などの会社の経費は湯水のように出て行って。(今でも女房にこのころのことを言われると首をすくめています)深夜目が覚めて、隣で眠る子供たちの寝顔を見ながら「この子たちが大きくなるまでこの酒蔵が倒産せずに持つだろうか?」と眠れなくなったものです。それでも、身を削るような思いで設備投資といくらしても定着しない人材投資を続けながら10数年をこのコンクリート製の仕込み蔵とともに過ごしました。
それでも、何とかかんとかそのつらい時期をやり過ごし、気がついてみると曲りなりに小規模仕込用のタンクもそろい、タンク毎の冷却装置もきれいに配管され、それなりに酒蔵らしい体裁を整えてきました。
売り上げも増え始め、杜氏制度ではなく若手の社員による通勤制の仕込みも定着し、なんとなく上手く行き始めました。ところがコストの安い大型仕込からわざわざ手のかかる小型仕込に変えていますからいくら販売量が増えても冬季に一度に沢山造る昔の方式には戻れません。
仕込み期間は結果として前後に長くするしかありません。秋と春の温度の高い時期にどうやって仕込み蔵の温度を低温に維持するかが課題になり始めた頃。知り合いの電気屋さんが「あれっ、この冷房機は5度まで下げられますよ」と教えてくれました。
なんと、夏場の酒の貯蔵室のクーラーとして利用していた冷房機がそれ以上に冷やす能力を持っていたんです。もちろん、建物は断熱してあるわけではありませんから外気温が20度を超すようなときには無理ですがそれ以下の時期なら電気代さえ無視すれば5度前後に保つことも可能だったんです。
実は私は父の死去とともに社外から突然社長になったものでこのあたりの個別の設備の能力とか使い方はその時点の担当者の言うがままで、その意味ではせっかくの設備をそのまま死蔵しているものや使いきっていなかったものも多かったんです。
それからは一瀉千里。次の年にはまず一室に断熱用発泡スチロールを室内に吹き付けて簡易の冷蔵仕込み室とし、結果が上々なのを見て翌年には主醗酵室。翌々年には酒母室。その間には冷却機も最新のものを加え、見た目のしょぼさを別にすれば能力的にも最新型の冷蔵仕込み蔵と遜色ないものになりました。
ある業界関係者からは「外気と遮断された要塞のような酒蔵。金がある蔵は違うねぇ」と皮肉られました。それまで100円ショップとホームセンターで手に入るものを基本的に使用するというポリシーを掲げ、素人のやっつけ仕事に毛の生えたような改造を繰り返してきた私としては反対に褒められたようななんとも面映い言葉でした。
気がついてみれば恨みの的だったあの仕込み蔵が私を救い支えてくれたんです。ある方が「前の仕込み蔵の壁なり屋根なり一部でいいから切り取って新しい蔵のどこかにはめ込んだら」と提案してくれました。
早速、工事責任者のところに言ってこの案を話してみました。「いいですよ。できますよ。歴史として残すんでしょ」と快諾してくれました。変な話ですが、その途端に25年のこの仕込み蔵との歳月が思い出されて、顔を見られたくなくて大急ぎでその場を後にしました。