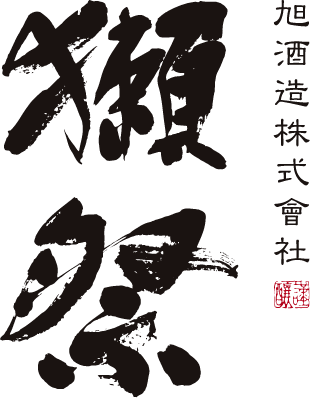テレビ・新聞等で報道されましたので、もうこれを読んでいる皆様は私どもが旭酒造株式会社から株式会社獺祭へ社名を変える覚悟を決めたことは、ご存じの方が多いと思います。
海外に行きますと特に言われるのですが、「お宅はビールメーカーの子会社か」とか「新聞社が親会社なんだろう」「親方日の丸だからこんなこともできるんだ」という誤解も有ったりして、説明に労力をとられるということもありますし、シンプルに、獺祭しかこの20年間造ってないんだから旭酒造という社名の意味がない、ということもあります。
ですから構想そのものは10年ぐらい前からありました。しかし長期的には社名変更は正しいとしても短期的には痛みを伴います。ラベルの変更や各種免許申請の変更、そして輸出が半分近くあるわけですから、各国のめんどくさい通関手続きの変更問題、実際中国本土などは一か月半程度の輸出空白期間ができてしまう予想です。そんなことがあって、つい先送りになり続けていたのが現状です。なかなか踏み切れませんでした。しかし、今やらなければ将来絶対できないと思い決断しました。
それは、これから「ますます海外の売り上げウエイトが増してくるだろうから」です。また、ここまで皆様から成長させて頂いた獺祭の立場として、海外を伸ばすことが使命だと思っているからです。今、旭酒造本体の年間の売り上げが195億円、決算期が違いますから獺祭Blueの売り上げは加算しませんでしたが、決算期が同一として日米合算計算すれば200億円を超します。この売り上げを頂いている酒蔵として、これから世界で存在感のある酒蔵を目指すことは日本国民の義務のように感じます。
象徴的に社内で話しているのは「売り上げ一千億を目指そう」というものです。今、トヨタとかパナソニックとか日本ブランドの中には10兆円組も何社かありますので「たかが一千億」に見えるかもしれません。しかし、獺祭のような立ち位置の商品で一千億越えのブランドはファッションでも食の世界でも寡聞にして知りません。獺祭が今ここで一千億に挑むことは価値があると考えています。
それに向けて、社名変更発表会当日にはいくつかの計画を社長からお話しさせていただきました。新蔵の建設計画、フランスが誇る三ツ星シェフであるヤニック・アレノさんとのコラボによるレストランのパリ店開店。ハリウッドのアカデミー賞会場での一夜限りの獺祭バー、オーストリアの誇る名曲「水辺のワルツ」を聞かせた「未来を作曲・獺祭」の万博オーストリア館での発表と発売、そして、先日ニュースになりました月での人間の生活を見据えての宇宙醸造計画酒「獺祭Moon」の発売計画!!(それぞれ詳細は私どものホームページに記載しております)
いずれをとっても獺祭のような小さな酒蔵にとって、40年前であれば「夢の、夢の、また夢」の計画です。でも20年前に獺祭が少し皆様に認知され始めた頃、「今、バッターボックスに皆様のお陰で立たせてもらっているのですから、たとえ大きな空振りに終わってもバットを振ります」と宣言して、ともすれば地域の中に縮んでいこうとする日本の伝統産業界の風潮に背を向けて、ここまで歩んできました。獺祭はずっと「バットを振り続ける覚悟」です。
☆2025.1.23社名変更挨拶(発表会当日、ワクワクする将来計画は社長が話しましたが、私がお話しした内容はこんな話でした)
旭酒造のここまで歩んできた物語をお話ししたいと思います。
それは、潰れた酒蔵の次男坊だった私の祖父・桜井喜一が故郷の光市を出て、山奥の村にあった酒蔵に職を求めたことから始まります。
やがて、やる気を失ったその酒蔵の持ち主から明治43年に酒蔵を借り受け、桜井酒場として酒蔵の経営を始めます。銘柄は地域の名前をとって「周東桜」とされました。そして、大正15年には正式に酒蔵を買い取り酒造免許も桜井喜一名義となります。この頃は地元の村を商圏とし、大八車で配達していたようです。商売は順調だったようですが、太平洋戦争の激化とともに企業整備による廃業の憂き目にあいます。
戦争から復員してきた、喜一の次男であり私の父である桜井博治とともに1948年に酒蔵を復活させ、旭酒造株式会社という新社名の下もう一度、歩み始めます。銘柄も「旭富士」と新しくなりました。
その後、1960年の祖父の死去により父の博治が二代目社長となり、戦後の経済成長の下、地元の村から山口県の東部地域に販路を拡大していきます。しかし、1973年の第一次石油ショックから業界全体に現在に至る長期低落傾向が始まります。その三年後の1976年に私・桜井博志が酒蔵に帰ったのです。
将来に不安を抱く私と高度成長時代の成功体験から逃れられない父・博治の間には衝突が絶えず、結局、私は酒蔵を首になります。父は本意ではなかったのでしょうが、父と子というのは感情的になりますと他人より始末に負えないということですね。
そのまま、私と父は仲を修復できぬまま、1984年の父の死去へと至ります。結局、勘当中の私が後を継いで三代目の社長に就任します。しかし、社長になってみてわかったのは10年間で売り上げ三分の一になってしまった旭酒造の姿でした。
何とか立て直そうと努力したのですが、1980年代に入って激化した酒蔵同士の販売競争で負け組になっていた現実もあってどうにもなりません。そのどうしようもない現実は私に東京市場の開拓へと駆り立てました。そしてそれは、普通の酒「旭富士」ではなく純米大吟醸「獺祭」の開発につながります。その頃、業界で純米大吟醸なんておとぎ話のような酒で量産技術も市場もなかったのですが、他に選択肢の無い私はただただその純米大吟醸と東京市場の成功に縋りつきもがき続けました。「山口の酒が東京で売れるはずがない」とずいぶん馬鹿にもされました。
おかげさまで、多くの失敗をしました。よく知られている話では「若手杜氏の育成のため、酒造りのない夏場の仕事を求めて開いたはずの地ビールレストランが上手くいかなくて、虎の子の杜氏に逃げられてしまう」といった大失敗も経験しました。そんな失敗だらけの旭酒造にもかかわらず、今、売り上げは、当初の一億にも満たない金額の二百倍近い195億まで成長しました。そして生産する酒はすべて「獺祭」になりました。
まさに逃げ場のない過酷な現実が今の旭酒造に導いてくれたのです。
さて、これからの旭酒造は、日本のプレミアムブランドとして世界に恥ずかしくない売り上げのボリュームを目指します。今、ここで日本酒という括りから飛び出して、旭酒造が日本発のプレミアムブランドとして世界に挑戦することは、ともすれば世界から見たとき、大量生産の経済合理主義だけを信奉し、新興国勢の猛追に負けて最近では輝きを失ったかに見える日本製品の見え方を変えると思います。
そして、その決意を込めて私たちは社名を変えます。
新しい社名は、株式会社獺祭です。
皆様ありがとうございます。
これからもよろしくお願いいたします。