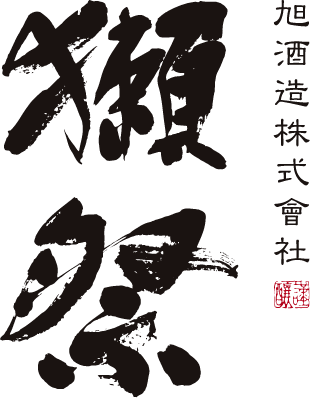一昨年の九月にオープンした獺祭BLUEのニューヨーク蔵。今回、テイスティングルームの展示の初期計画部分が完成しました。制作をお願いしたのはローカルプロジェクトという会社です。この会社は皆さんもご存じのところではニューヨーク近代美術館のモーマとかコカ・コーラの本社とかの来客向け展示を請け負った会社です。ちなみに、ジョージアのコカ・コーラ本社の展示は有料ですが一般客に開放されていて、それはすごいです。話のタネにアメリカに行かれる方は一見の価値があると思います。
ただのマス・プロダクトのアメリカ大衆文化の塊のようなコカ・コーラが見学後は一転して奥深い味わいをもって魅力的に見え始めること確実です。ということで、ジョージアまで足を延ばせない人は、ぜひニューヨークの獺祭BLUEのテイスティングルームを見学にいらっしゃいませんか。
この展示を計画する上で重視したのは「如何に獺祭の哲学を表現するか」です。「手間」に代表される「造る」ということを大事にする獺祭の考え方は、ある意味アメリカが持っている「製造はマーケティングと比べて下のもの」そして「合理化・標準化・大量処理・機械化」こそ重要というアメリカの考え方と対極にあります。この「手間」を大事にする表現を推し進めることは、アメリカ文化を否定することにもなり、危険性は大いに承知しながら推し進めた方向です。
しかし、簡単には出来上がりませんでした。英語のできない私がアメリカの制作会社と渡り合って作るのです。説明し説得し、やっと漕ぎつけて、でも見本を作ってみると最初のまま何も変わらず。思わずへなへなとやる気が失せてしまうような経験も幾つもしました。むつかしいものですね。
でも、その結果はまあまあのモノになりました。もちろん、まだ不満はいっぱい有りますけどね。この辺りは「獺祭らしく」、今のモノが最善で間違いを認めないのではなく、直していきたいと思います。
見に来てください。